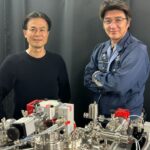仕事帰りの人たちが、のれんをくぐって立ち寄る。店の中からは笑い声と「おつかれさま」の声。

そんな日常の風景の中に、ヨシックスホールディングスの原点があります。
1998年、名古屋・押切で創業者の吉岡昌成氏が開いた小さな居酒屋「や台や」。「自分が行きたい店をつくりたい」その思いで始めた店は、気取らず入れる温かさが評判を呼び、やがて本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」など全国に広がる「や台やグループ」へと成長しました。
建築業から飲食へと転身し、「“あたりまえや”を当り前に」という言葉を企業の真ん中にすえて歩んできた株式会社ヨシックスホールディングス。
常務取締役である伊達 富夫(だて・とみお)さんに、同社の成長の裏側と変わり続ける力について伺いました。

目次
建築業から始まった「飲食への転身」
「最初は、お弁当屋さんの内装をつくる建築業の会社でした」
ヨシックスホールディングスの原点は、建築内装業「ヨシオカ建装」。創業者の吉岡昌成(よしおか・まさなり)さんは大阪・阿倍野の出身で、1980年代にお弁当チェーンの施工を手がけながら名古屋に拠点を移しました。

しかし、コンビニの台頭によりお弁当ブームは終息。仕事が途絶える危機の中で、吉岡さんは新しいビジネスを模索し始めます。
当時のことを、伊達さんはこう振り返ります。
「そのころ、居酒屋が伸びていたんです。施工の仕事を通じて飲食の世界に触れていったこともあり徐々に、“自分でもやってみたい”と思うようになったそうです」
こうして始まった飲食業。最初はフランチャイズとして他社ブランドを運営していましたが、次第に「自分たちの店を持ちたい」という思いへ。ただ、おしゃれなダイニングバーを開いたり、他にも「うどん」など複数を手がけたものの、思うようにはいきませんでした。
「最後に、自分が行きたい店をつくろうと思ったそうです」

1998年、名古屋市西区押切に開店した「や台や」1号店。 “誰でも気軽に立ち寄れて、明日の活力になるような場所”を目指したお好み焼き鉄板居酒屋は、地域の人々の心をつかみました。
運命の出会いが生んだ拡大の波
1号店の成功の裏に、もう一人のキーパーソンがいました。それが現代表取締役社長の瀬川雅人さんです。

「彼はもともとデザイン会社やコンサルティング会社で仕事をしていたんです。喫茶店好きで、たまたまうちの店を見つけて“面白そうだな”と入ってきた」
飲食業未経験ながら、整理力と実行力を兼ね備えた瀬川さん。吉岡さんの現場主義と瀬川さんの論理性が出会い、ヨシックスの成長が加速します。
2000年には「や台ずし」1号店を名古屋で開業。「や台や」で培った“開放感のある空気”をそのまま寿司業態に持ち込み、寿司をもっと気軽に楽しめる新しい居酒屋文化をつくり出しました。

「同じ場所でも、時代に合わせて業態を変える。たとえ時代の波をくらって事業の雲行きが怪しくなっても、致命傷になる前に変えられるのがうちの強みです」そう話す伊達さんの声には、静かな確信がにじみます。
“失敗を恐れず変化する”という文化が、同社の生存力を支えています。
「“あたりまえや”を、当り前に」理念が息づく組織文化
ヨシックスの理念は、創業以来一貫しています。それは「“あたりまえや”を、当り前に」。
「会長も社長も、ものすごく真面目なんです。やるべきことをやる。それをずっと愚直に続けている」
真面目さは押しつけではなく、行動で伝える文化。
会長は今でも店舗を見回り、社長は全国を飛び回って出店を確認します。社員たちはその背中を見て、“努力が当たり前”という空気を自然に共有しています。
人を育てる“寿司居酒屋”という現場

「や台ずしでは、60席以上の店でも寿司職人1人で回しているんです」
この効率的な設計が、同社の強み。お寿司を待つ間に居酒屋メニューを楽しめるため、回転率も高く、価格も抑えられる。その裏には独自の育成文化があります。
「未経験で入ってきたスタッフでも、“握りチェック”に合格すればお寿司を握れるようになります」
修行ではなく、学びの場としての寿司。実際の仕事の現場でスキルを教え、早期に現場に立てる仕組みを整えることで、スタッフのモチベーションも高まります。今では約4割のスタッフが入社後に寿司を握れるようになったといいます。
あるスタッフは「寿司を握って“ありがとう”と言ってもらえる。それが嬉しいんです」と笑顔で話します。

この言葉には、伊達さん自身の実感も重なります。入社当時はホールに立ち、お客さまから直接「ありがとう」と言われた経験が、今も自分の原動力になっているといいます。
ヨシックスが育てているのは“職人”ではなく、“人として輝く働き手”。その輝きは、現場で交わされる一言の「ありがとう」から生まれているのです。
課題に立ち向かう柔軟な経営
近年、世界的な資源価格の高騰と人手不足による賃上げ圧力などにより、原材料や人件費が上がり続けている飲食業界。そんな業界の共通課題に対し、ヨシックスは真っ向から挑みます。
安易な値上げではなく、メニュー構成やロス削減による工夫で利益を確保。モバイルオーダーは“効率化”ではなく、「店員さんが忙しそうで声をかけづらい」というお客さまからの声を受けて導入しました。
テクノロジーは人の心を離さないために使う。こうした顧客体験重視のDXが、次の時代のヨシックスを支えています。
居酒屋がつくる「社会の明るさ」
「もし居酒屋がなくなったら、世の中は暗くなると思うんです」。伊達さんは静かにそう語ります。
同社は「居酒屋」という文化の社会的意義を真剣に捉えています。「気軽に集い、笑い、元気を持ち帰る」それが人と社会をつなぐ灯になるからです。
「時代に合わせて業態は変わっても、目指すのは“元気を持って帰ってもらう”こと」
建築と飲食の両輪で磨かれた適応力に加え、次の時代を見据えた“第三の柱”も模索中。その先にあるのは、誰かの笑顔が見える未来です。
「“あたりまえや”を、当り前に」
このシンプルな言葉の裏には、時代が変わっても揺るがない信念があります。建築業から始まり、居酒屋文化を築き、社会に“元気”を届ける。
ヨシックスホールディングスは、これからも「変化の中に普遍を見つける企業」として、人と社会を明るく照らし続けていきます。
最も印象に残った言葉
「時代に合わせて業態は変わっても、目指すのは“元気を持って帰ってもらう”こと」
企業情報
会社名:株式会社ヨシックスホールディングス
取材対象者:常務取締役 伊達富夫さん
設立年月:1985年
社是:あたりまえやを当り前に
事業内容:持株会社として事業子会社の支配・管理のほか、企業経営に関する助言・指導を主に行う
URL:https://yossix.co.jp/
所在地:愛知県名古屋市東区徳川1-9-30