
須賀川市は今年2025年5月、市内公共施設の今後の在り方を示した「公共施設マネジメント素案」を公表した。その中で、市立博物館は収蔵機能に特化し、展示などの博物館機能は約10キロ離れた長沼地区の歴史民俗資料館に移すという案が示された。この案に異を唱えたのが長年須賀川のガイドとして第一線で活躍してきた宗像正夫さん。「福島県初の公立博物館という“価値”を失いかねない」と警鐘を鳴らす。市が描く再編方針に、どんな懸念があるのか、今回、須賀川市立博物館友の会の会長も務める宗像さんにじっくりお話を伺い前後編でお送りする。
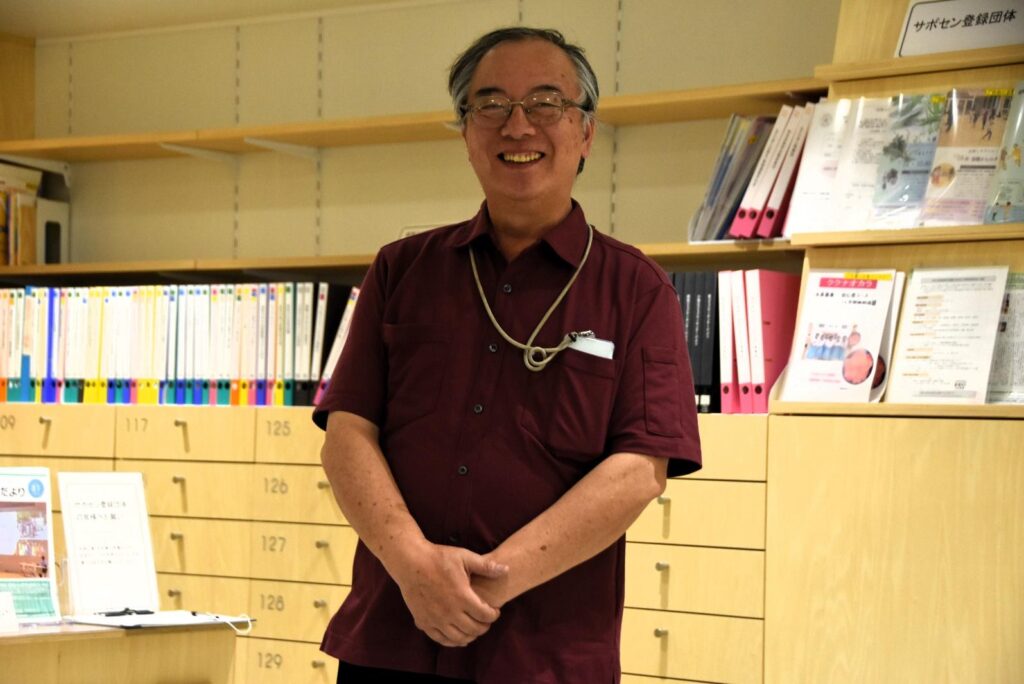
―最初に、公共施設の再編について耳にしたのはいつ頃でしたか?
今年の5月ですね。5〜6年前にも長期的な構想のようなものは出ていましたが、老朽化した施設を全部建て替えようとすれば何億とかかるわけで、市長も「議会と話し合いながら決めたい」と話していました。
平成の大合併で、須賀川・長沼・岩瀬の3市町村が統合して新しい須賀川市が誕生してから、今年でちょうど20年になります。その時に、将来を見据えた統廃合の方針をきちんと持っていればよかったのですが、結局、現状維持のままここまで来てしまった。たとえば旧長沼町にはもともと歴史民俗資料館や図書館がありましたが、それにも手をつけず、今に至っています。
―今回の案で、市立博物館を収蔵施設とし、博物館機能を歴史民俗資料館に移転するという方針が示されました。これを聞いて、どこに一番問題を感じましたか?
まず一番に思ったのは、「今の博物館の価値をまったく理解していない」ということです。須賀川市立博物館は、私たち観光ガイドにとって街歩きや歴史散策のスタート地点としてとても重要な場所です。また、あの周辺は鎌倉・室町時代の城跡を中心にコンパクトにまとまった、まさに須賀川の“顔”とも言える場所。全国いろんな博物館を見てきましたが、個人的には博物館というのは一般的に環境のいい場所に建てられていることが多いという印象を受けています。府中公園(東京都)内にある博物館に行ったときも、まさに理想的な環境だと感じました。須賀川市立博物館も、都市公園100選に選ばれた翠ヶ丘(みどりがおか)公園に隣接していて、環境面では非常に優れている。心身の健康にもいいし、まさに最適なロケーションです。
―立地的にも、博物館の存在が町全体の魅力を引き出しているのですね。
そうです、あの場所は地盤も非常に強い。東日本大震災のとき、ちょうど雛祭りの展示をしていたのですが、三人官女の人形が一体倒れただけ。他の公共施設が大きな被害を受けた中で、博物館の被害はほとんどなかった。そんな安全性の高い場所をわざわざ手放す必要があるのか、疑問ですね。
―観光客の視点から見ても、駅から離れた長沼地区への移転は不便に感じますか?
当然そうですよ。知らない町に行ったら、まず博物館を訪れるというのが旅行者の基本的な行動じゃないですか?「どんな町だろう」「どんな歴史があるのだろう」と把握してから、他の名所に行くものです。だから、駅からも遠く、アクセスの悪い場所に移すなんて、正直言って「何を考えているんだ」って言いたくなります。
―平成の合併以降、市内には博物館施設が併存してきました。その点についてはどう考えていますか?
そうですね、今でも「あの時に長沼の施設を分館にしておけばよかった」と話している人はいます。今回の案では、図書館の再編も俎上(そじょう)に載っていますけれど、人件費削減のために統合するってむきもあって、それもどうなのかなと思います。「働き方改革」みたいな制度を導入すれば職員の休暇も増やせる。「1人分で何百万円浮きました」てね。目先の話ばかりして、「今日の1,000円を惜しんで、未来の100万円を失う」ことになるじゃないかと。古い中国のことばに「一年の計は穀を植うるにあり、十年の計は木を植うるにあり、百年の計は人を育てるにあり」(管子)というフレーズがあります。つまり、人を育てることが最も重要だということです。
須賀川市歌では「文化の都、自治の町」と謳(うた)っていますけど、現実がこれではちょっと寂しいですよね。「歴史の町」と言うのであれば、もっとやるべきことがあると思います。
―双方の施設では、収蔵や展示の運用方法に違いがあるのでしょうか?
はい。長沼の方は“歴史民俗資料館”という名前の通り、民具や長沼焼という焼き物、人形などの民俗分野に特化した展示を行っています。長沼と須賀川では、もともとの歴史的背景や文化が違うので、意識していなくても「色が違う」っていうのは、やっぱり出てきますね。
―市内には、松尾芭蕉の来訪300年を記念して建てられた「風流のはじめ館」もあります。
風流のはじめ館は文化施設としての機能はありますが、施設上、博物館のような本格的な収蔵庫は置けません。物置やバックヤードのようなスペースはあっても、温湿度管理が必要な貴重資料の保管には不向きです。市の担当者の中には、当時この施設の開設に尽力した方もいて、大切な資料は博物館に預けて、風流のはじめ館では借り受ける形で展示するなど、工夫しながらなんとか運営してきました。
―駅から離れた長沼地区に博物館機能を移すことで、市内全体の回遊性を高めようという意図があったのでしょうか?
それはちょっと現実的ではないと思います。長沼方面には路線バスは運行していますが、本数が少ないですし、タクシーだと駅から片道で6,000〜7,000円もかかるそうです。往復すれば1万円を超える計算ですよ。交通の便が悪い場所に移して、どうやって人を呼び込むのか。回遊性を高めるどころか、アクセスの悪さで来館者が減ってしまうでしょうね。





