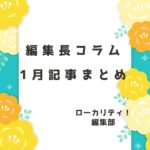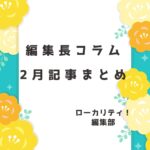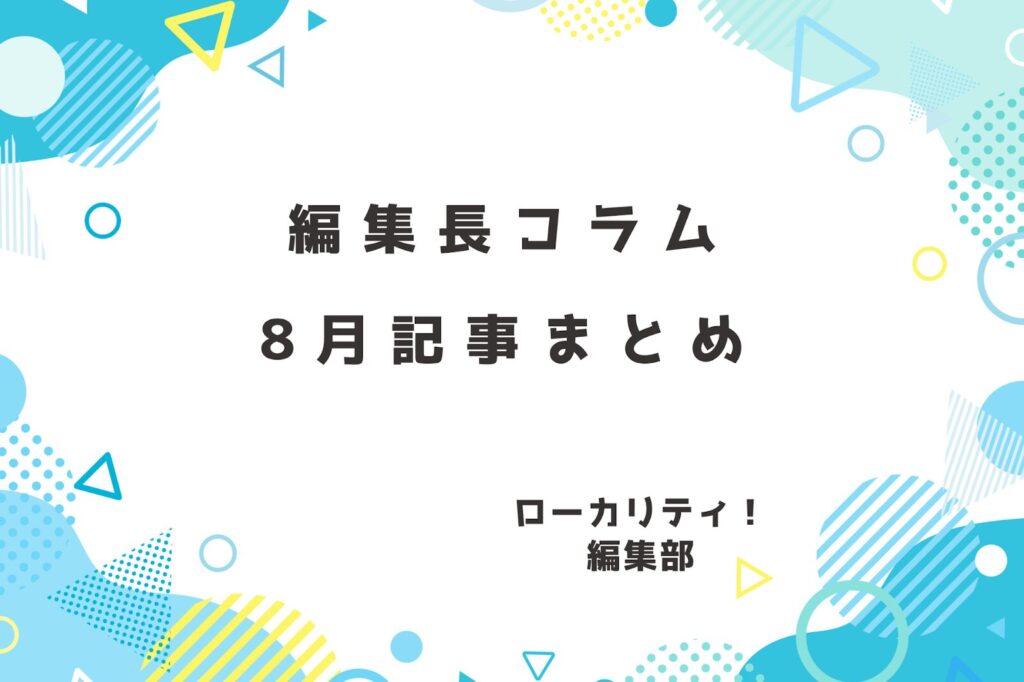
8月のローカリティ!は、まるで「知らない世界へと小さな旅に出る」ような記事が集まりました。
台湾の廟(びょう)に眠る日本人飛行兵の記憶から、足がすくむほどの細いつり橋を渡る冒険、川底にひっそりと咲く白い水中花。
一方で、沼に手を伸ばして摘むジュンサイや、「限定10杯」のために試行錯誤を重ねたクリームソーダ、地元に愛されるパンやドーナツなど、食をめぐる物語も豊かです。
花笠まつりの熱気や、震災と原発事故の避難先でも受け継がれる祭りの太鼓の音、野球の原点をたどる館や災害現場からの学びは、どれも地域の記憶と未来を結び直してくれます。
そして夜の灯台や星空写真展が教えてくれるのは、暗闇の中でこそ見える光の物語。
遠くの地で生まれた祈りから、身近な台所のぬくもりまで。
今月は「知らなかった世界」と「そこに息づく人の思い」が、そっと私たちの心を揺らすような記事がそろいました。
目次
異国で息づく日本兵の記憶と祈り
今後の海外からの記事もとても楽しみにしています!
息をのむ冒険と自然の魔法
自然の奥へ誘う写真に、思わず足がすくむ感覚まで伝わってきました。
夏の川底に咲く小さな白い花が、知らない世界の静かな美しさを教えてくれます。
小さな台所から生まれる味と物語
こうした地域の体験記事をもっと読んでみたくなります。
「納得のいくものを届けたい」という思いが伝わってきて胸が熱くなりました。
庄内の夏を支える一杯の物語が、食文化の奥行きを感じさせます。
市場の熱気や人の声まで浮かんでくるようで、食の物語としても魅力的です。プロのような見出しです!
作り手の思いがしっかり伝わってきて、読む人の心をやさしく満たします。
現場性が高く素晴らしいです。次回は取材を受けた方の顔が見えたらもっとすてきですね。
響きあう祭りと人の絆
街全体がひとつになって踊る瞬間の熱気が写真からも伝わってきます。
文化は生き物、祭りは、地域再生の象徴であり、復興の原動力。まさにその通りですね。
時をこえて学ぶ土地の記憶
100年前から続く物語をしっかりと掘り起こしてくれて感謝です。
現場からのリアルな声が、私たちに防災の未来を考えさせてくれます。
夜の光が紡ぐ静かな物語
静かな夜の海に光がともる時間が、とても印象的でした。
石川町や湖南町など、自分が知らなかった地域の世界の広がりを感じさせてくれるきじでした。まさにローカリティ!らしい記事です。
旗を掲げ心に火を灯す
9月20日、21日、私たちイーストタイムズのメンバーは、創業のきっかけとなった東日本大震災の被災地を訪れました。仙台空港から始まり、名取市閖上、仙台市荒浜、石巻市鮎川、女川町、石巻市旧大川小学校、南三陸町へ。
あの日の記憶と、そこから生きてきた人々の物語をたどる旅でした。
私たちは、自分たちが「何を大切にしているか」を改めて話し合い、確認しました。
あらためて思うのは、私たちローカリティは、災害や被害の数字ではなく、「どう生きてきたか」という人の物語をずっと追いかけてきました。これこそが、ローカリティの根っこにある特徴だと感じます。
たとえば荒浜。
故郷を失いながらも、この地の名を残そうと自らの心に火をともして立ち続けた人たちがいました。黄色いハンカチを掲げ、記憶をつなごうとしたその姿は、旗を掲げるという行為の重さを教えてくれました。
また、鮎川でも、捕鯨の町としての誇りを胸に、失われた日常を取り戻そうと心に火をともした人たちがいました。海とともに再び生きようとするその背中から、私たちは諦めずに立ち上がる力を学びました。
14年経った今も、「諦める方がどれだけ簡単か」という現実があります。
それでも旗を掲げ続ける覚悟は、決して浅い感情からは生まれません。
誰かに頼まれたのでもなく、自分の人生の選択として「やる」と決めた人たちの心に灯った火こそが、私たちの旗印の起点になっています。
私たちは「諦めない」を選んできた人たちの背中に学びながら、自分たちもまた旗を掲げてきました。
これからもそれを受け継ぎ、まだ見ぬ物語へと「火」をともしていきます。