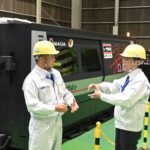サラヤ株式会社(以下、サラヤ)は1952年に手洗いせっけんメーカーとして誕生し、現在は家庭用洗浄剤、食品・公衆衛生、医療・福祉、海外事業の四本柱で事業を展開しています。創業以来、社会課題をビジネスで解決する姿勢を貫き、手洗い文化の普及や植物由来洗剤の開発、さらには植物由来でカロリーゼロの甘味料「ラカントS」の市場創出など、業界の枠を超えた挑戦を続けてきました。今回は、広報宣伝統括部 統括部長の廣岡竜也(ひろおか・たつや)さんへの取材をもとに、同社の取り組みとその価値に迫ります。

目次
デジタル時代の到来を感じ、広告代理店からサラヤへ
廣岡さんは大学卒業後、広告代理店で約8年間勤務しました。新聞・雑誌・テレビが主力だった当時、印刷物の制作が業務の中心で、長時間労働が常態化していました。Windows 95の発売を機にインターネットが急速に普及し始めたものの、当時勤めていた会社ではデジタル施策が軽視されていたと言います。
サラヤへの転職の理由について「印刷偏重のままでは時代に取り残されると感じました。新しい潮流を実践できる環境へ移る必要があると考え、サラヤの求人に応募しました」と廣岡さんは語ります。
サラヤの価値を正しく伝えるため、広告戦略の刷新へ
入社当時のサラヤは、売上規模に対して過大なテレビCMを行っていましたが、現社長の就任を機に広告費は売上に適切に連動する形で再設計されました。その際、廣岡さんが広告戦略担当として主導し、テレビ中心から雑誌やインターネットを活用した戦略へとシフトしました。
「限られた予算を最も響く相手に投じるべきだと考え、リーチ(投稿などを見た人の数)よりエンゲージメント(投稿などに対するアクション数)を重視する戦略に切り替えました」と廣岡さんは語ります。
コスト効率と的確なターゲティングを両立させる施策は、資源制約のある中小メーカーにとって現実的な戦略と言えます。
肌へのやさしさに光を当てたブランド再構築
1971年発売の「ヤシノミ洗剤」は環境に配慮した製品としては先駆けでしたが、調査の結果、消費者が最も価値を感じていたのは手荒れ対策でした。同社は洗浄力競争から距離を置き、ユーザーの悩みに寄り添う製品開発へ切り替えました。
「大手と同じ土俵で勝負しても意味がありません。我々は他社が行っていない“肌へのやさしさ”を強みに、雑誌やコミュニティーを通じて丁寧に発信しました」と廣岡さんは語ります。
非を認める力で、獲得した信頼
2004年、ヤシノミ洗剤の原料のひとつであるアブラヤシ(パーム油)の栽培が、ボルネオ島の自然を破壊し、そこに暮らす野生動物たちが行き場を失っているという内容を扱ったテレビ特集によって、同社は批判を受けました。社長は至らなかった点を認め、即座に現地調査と対策を公表しました。
「問題の矢面から逃げるのではなく、事実を直視し行動で示すことが企業の信頼を守る近道だと思い、行動しました」と廣岡さんは振り返ります。
透明性と迅速な対応は、炎上をプラスの機会に変える危機管理の模範となり、同社の社会的評価向上にもつながりました。

協働プラットフォームで他者と手を携え、環境問題へ向き合う
ボルネオの経験を踏まえ、同社はNPOや自治体・企業と連携する協働型プラットフォームを構築しました。2025年大阪・関西万博では特定非営利活動ZERI JAPANが出店するパビリオン「BLUE OCEAN DOME」の運営を支援し、海洋課題を啓発しています。
「環境問題は一社だけで解決できません。他者と手を携え、発信と行動の場を共有することが不可欠です」と廣岡さんは強調します。
売り上げの1%を環境保全へ。サラヤ独自の行動意思
同社は売上の1%を環境保全に対する取り組みに充当する仕組みを2004年から継続しています。前例のない仕組みに対して当初は、社内で懸念もありましたが、ブランド力向上と売り上げ増加により投資効果が実証されています。
「社会課題への先行投資は長期的に企業価値を高め、優秀な人材や取引先の信頼を呼び込んでくれます」と採用の観点でも効果があったと廣岡さんは語ります。

企業市民としての成長のあり方
更家悠介社長は「企業も社会を構成する市民である」と明言し、事業活動のあらゆる段階で社会・環境負荷の低減を図っている同社。
「資源を独占せず、社会とともに価値を創出する企業こそが次代を生き残っていく」
企業市民の視点を経営に組み込む姿勢は、ESG投資(環境(Environment)、社会(Social)、企業統治(Governance)の3つの要素を考慮して行われる投資)や消費者選好の変化に対応するうえで不可欠な要素となっています。
事業を通じて描く、環境経営と未来像
同社が目指すのは、衛生・環境・健康といった生活基盤を支える領域で、協働と当事者意識を循環させる“次世代型エコシステム”の確立であると言えます。特に売り上げの1%を環境投資に回す仕組みは、社会的インパクトと企業成長が相乗効果を生むことを実証してきました。今後は海洋保全を起点に、地域特性に応じた水循環・資源循環モデルを各地で展開し、国や業界の枠を超えた連帯を加速させる計画です。
森から海へ、衛生から食へ――同社の挑戦は、より広いステークホルダーを巻き込み、誰もが恩恵を受けられる持続可能な社会の実現へと向かっています。
聞き手、執筆:木場晏門
【2025年12月16日訂正】
2025年7月24日公開の本記事において、 本文中に誤りがありましたので訂正いたします。
(正)ヤシノミ洗剤の原料のひとつであるアブラヤシ
(誤)ヤシノミ潜在の原料のひとつであるアブラヤシ
校閲が行き届いておらず、誤記がありましたことをお詫びするとともに、ここに訂正いたします。
情報
サラヤ株式会社
HP:https://www.saraya.com