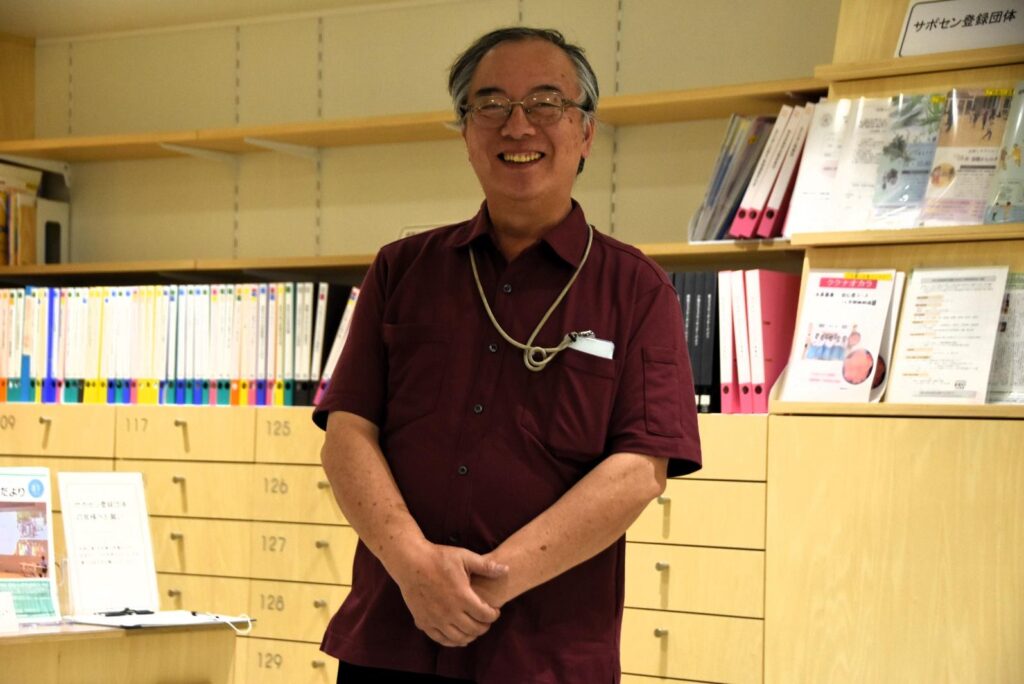
須賀川市では5月、市内公共施設の今後の在り方を示した「公共施設マネジメント素案」を公表した。その中で、市立博物館は収蔵機能に特化し、展示などの博物館機能は約10キロ離れた長沼地区の歴史民俗資料館に移すという案が示された。この案に異を唱えたのが長年須賀川のガイドとして第一線で活躍してきた宗像正夫さんだ。「福島県初の公立博物館という“価値”を失いかねない」と警鐘を鳴らす。市が描く再編方針に、どんな懸念があるのか、今回、須賀川市立博物館友の会の会長も務める宗像さんにじっくりお話を伺った。前後編でお送りする。

―お話をうかがっていると、須賀川の文化行政が少しずつ後退しているような印象も受けます。宗像さんご自身としては、博物館は現状維持が理想だとお考えですか?それとも、さらに発展させていくべきだと?
私の考えでは、「適正化」がキーワードだと思っています。「適正化」というのは、施設が本来の目的をきちんと果たせるように機能を整えるということ。節約や削減ではなく、博物館や資料館でいえば資料の収集・保存・研究・公開・教育といった役割を“効果的に”果たせるようにすることが重要です。やはり色んな機能を持たせて、時代に合った形にしていくのが私の考える「適正」。現在の博物館は正直、狭すぎます。収蔵庫もなく、展示スペースも足りない。学習スペースも、椅子を並べただけの簡易な閲覧コーナーがあるだけです。もっと資料もそろえたいし、来館者がくつろげる喫茶スペースのような場所も欲しい。たとえば、東京都の府中市郷土の森博物館はエントランスがとても立派でしたし、この春開館した郡山市歴史情報博物館も素晴らしかった。ああいう施設が理想ですね。
―以前から建て替えの構想があったと聞きました。
そうです。今から15年ほど前、ちょうど築40年を迎えた頃、「そろそろ限界ではないか」と建て替えの話が持ち上がったことがありました。ただ、その直後に東日本大震災が起こって、それどころではなくなってしまった。もしあの時、建物に大きな被害が出ていたら「この際建て替えよう」という話になっていたかもしれません。
―公共施設の再編全体について、ポイントはどこにあると感じますか?
「民間活力の導入」がそのひとつです。要するに、引き受け手がいれば施設を売却し、いなければ取り壊すという考え方です。実際、民間に任せてうまくいった事例もあります。
たとえば、今回の再編対象のひとつに市民温泉(1983年供用開始)があります。これについては、高齢者の方々から「安く入れるお風呂がなくなったら、家に閉じこもってしまう」「認知症が進んだら、医療費がどれだけかかると思っているの?」といった切実な声が出ています。温泉を残すことで健康寿命が延びる、そういう視点からの考察ももっとしてほしいですね。
―博物館を将来に残していくためには、今どんな取り組みが必要だと思いますか?
資金がないなら、集めればいいんです。たとえばクラウドファンディングを立ち上げるとか、ふるさと納税を活用するとか。入場料のほかにも寄付金や篤志金の制度を整えて、「市民で博物館を支えよう」という空気をつくることが大切です。
「資料にカビが生えそうです」と本気で訴えれば、きっと動いてくれる人がいる。「それなら俺が1万円出すよ」って言ってくれる人がいると思うんです。でも、今はそういう動きが見えない。それどころか、「もう潰す方向だ」っていう空気がある。そうなったら、何もできなくなってしまう。まずは「残してほしい」という声を集めるところから始める必要があります。
過去には、市が率先して基金や補助金を探し回ったこともありました。今だって国の制度や支援策を上手に使えば、道は開けるはず。建物のハード面と、展示・活用といったソフト面は切り分けて考えるべきですし、コスト削減ばかりを優先するのではなく、まずは「やれることをやる」。その上でマネジメントするのが、行政の責任だと思います。
―最後に、市民や読者に向けてメッセージをお願いします。
私は須賀川市立博物館の機能移転や縮小には断固として反対しています。市民憲章にも「よく学び、教養と文化を高める」とあるように、博物館はその核となる施設です。「文化のまち・すかがわ」を標榜(ひょうぼう)するのであれば、なおのこと、その文化を守り、次世代に継承するための拠点が必要です。
博物館が収集・研究・保存してきた資料や情報は、誰のものでもない。市のものでも、職員のものでもなく、すべての市民の財産です。すべての人がその資料を自由に利用できる権利がある。だからこそ、私たち一人ひとりが博物館を支える当事者として、未来のために行動するべきだと思います。そうした環境を、市全体で育んでいくことが大切です。
―ありがとうございました。






2 件のコメント