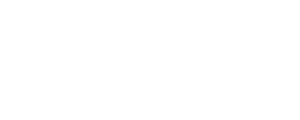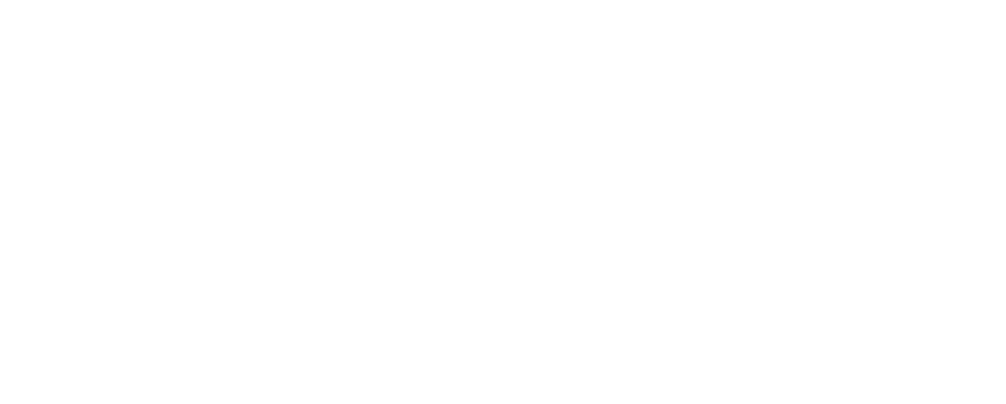筆者の連載記事である『自分の手で作る酒。密着! 大学生の日本酒づくり』において、秋田大学の学生とともに稲の種まきから日本酒の製造・販売までを行っている、秋田清酒株式会社の代表取締役社長、伊藤洋平(いとう・ようへい)氏(51)に会社について伺った。
目次
【創業150年以上! 時代とともに歩む2つの酒蔵と1つの会社】
秋田清酒株式会社(以下、秋田清酒)には出羽鶴酒造株式会社(以下、出羽鶴酒造)と刈穂酒造株式会社(以下、刈穂酒造)の2つの酒蔵がある。秋田清酒はこの2つの酒蔵で作られた日本酒を瓶詰めし、貯蔵・販売を行う企業である。
江戸時代後期の1865年から、伊藤家12代目の伊藤重四郎(じゅうしろう)氏によって酒造りが始まった。当時は「ヤマト酒造店」という屋号の個人事業で、創業から50年続いた。
1913年に「ヤマト酒造店」は「出羽鶴酒造」と名前を変え、株式会社になった。
同年、隣町の神宮寺町(現大仙市神宮寺)で、当時の社長である伊藤恭之助(きょうのすけ)氏(伊藤家13代目)と仲間が資金を出し合い、刈穂酒造を設立。
第二次世界大戦中は酒造りを一時中断していたが、戦後に復活した。そして、高度経済成長期に日本酒の需要はピークを迎えた。当時、出羽鶴酒造は1升瓶で100万本生産し、刈穂酒造はその半分ほどを生産していた。非常に多い生産量と設備の老朽化で瓶詰め工程が追いつかなくなり、設備更新との瓶詰め工程の効率化が行われる。その過程を経て、瓶詰め工程や貯蔵、販売を統一した企業である秋田清酒が誕生した。

【出羽鶴酒造の酒造りのこだわり】
出羽鶴酒造では、創業者の伊藤重四郎氏の思想を元に酒造りを行っている。当時は米も自分たちで栽培し、蔵人も地元の人であった。つくり方は江戸時代から行われている生酛仕込(きもとじこみ)である。生酛仕込とは、水・米・微生物のみで酒をつくる方法である。秋田県で行われていた生酛仕込は、秋田の風土や環境を活用し、冬の低い気温の中でゆっくりと発酵させ、丁寧に行われていた。出羽鶴酒造のお酒はほとんど秋田流の生酛仕込でつくられている。
生酛仕込やその派生系の山廃仕込は玄人に好まれることが多いが、出羽鶴の水は柔らかく、比較的飲みやすい日本酒になる。
その中でも「やまとしずく」というブランドは完全生酛仕込でつくられており、地元栽培のお米を使用している。販売店も商品管理をしっかり行ってくれるお店に限定している。

【きっかけは社員! 酒造り以外の挑戦】
秋田県には活動的な酒蔵が多い。酒蔵をギャラリーにしてみたり、酒蔵を開放しツアーを行っていたりする。秋田清酒も自社で酒米を栽培したり、産学官での連携を行っていたりする。
秋田清酒の通販サイトを見ていると「門喜窯(もんきがま)」という窯元の酒器が売られていた。これは刈穂酒造の蔵人が作った、日本酒を楽しむための器である。この蔵人は冬は刈穂で酒をつくり、夏は農業をしながら陶芸を行っている。そのことを知っている伊藤社長は、秋田清酒の通販サイトでの販売を提案した。
また、フェイシャルマスクも販売されている。これは以前在籍していた社員がきっかけでできた商品である。その社員の大学の同級生が神奈川県のコスメ企業に務めており、日本酒の成分を原料としたコスメ商品の企画があった。「社員同士のやりとりから企業同士のやりとりに、自然な形で移り変わり、商品化したんですよ」と伊藤社長は教えてくれた。
風通しがよく、体系にこだわらない柔軟な社風を感じた。
【危機への挑戦】
新型コロナウイルスが蔓延している中で、お酒を飲む場面が制約されている。「同じようにはいかないかもしれないけど、状況が好転したら楽しくお酒を飲んでもらえる場面を作っていかないと、と考えています」と伊藤社長は語った。「美味しいお酒をつくるのが前提ですが、製造・流通・提供するお店で協力して建て直さないといけません」と考えを教えてくれた。

【100年後に向けての取り組み】
「『3代先の人たちがお酒をつくることができる状況』を作っていかないといけない」と伊藤社長は話してくれた。酒造りには自然や原料、人材など、様々な環境が必要となる。事業が続けられる環境を残すために、大学生と米から酒造りを行ったり、酒造りにおける二酸化炭素の削減について考えたりしている。 伊藤社長は「酒蔵が残るには味だけでは足りない」とその考えを教えてくれた。次世代が事業に価値や面白さを感じ、「継ぎたい」と思われなければ途絶えてしまう。そのためにリスペクトされる企業を目指している。企業の考え方や地域との関わり方などが定まっていないと、次世代はなかなか継続しようと思えないかもしれない。最後に伊藤社長は「美味しいことは前提だが、蔵を残すためには味以外の要素も同様に重要です」と話してくれた。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー