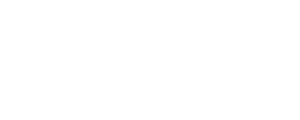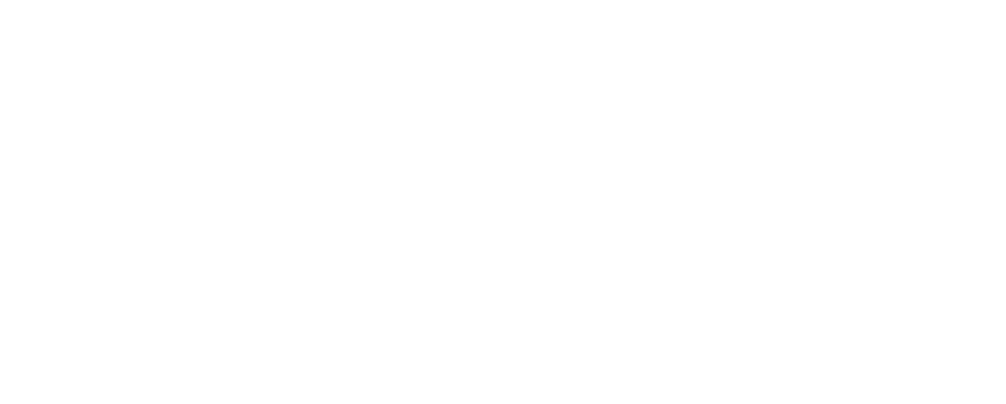和歌山市和歌浦西にある紀州東照宮で毎年5月に行われる「和歌祭(わかまつり)」という祭礼がある。和歌祭の中で、母衣(ほろ)と呼ばれる釣り鐘状の竹の骨組みに布を張ったものを背負い、「所望(しょも)、所望」の掛け声を受けてその場で勢いよく回転させるという演舞があるのだが、披露される演舞と母衣の形をみるとなんだかジブリの世界を思いだす。独特な雰囲気がそう感じさせるのだろうか?

2022年5月「和歌祭」の創始400年の節目として和歌祭四百年式年大祭が大々的に行われた。見学していた80歳の女性は「街なかで、母衣をみて若い頃を思い出して感動して涙が出た」と語っていた。
歴史ある和歌祭だが、その中でも見た目、演舞共に強いインパクトを感じられるのが母衣の特長だ。
そんな母衣を作る為にわざわざ竹を育てることに取り組んでいるという話を聞き、和歌祭で母衣を制作している団体の代表 中野 淳(なかの・あつし)さんに母衣へのこだわりをインタビューしてみた。

中野代表は、毎年5月に行われる「和歌祭」を前に、母衣の準備をメンバー達とすすめている。
母衣の骨組みは、「真竹」という節間が長いのが特徴である希少な樹種を使うのだそうで、以前に使っていた「孟宗竹」とくらべ軽く、下から上まで粘りやしなりが比較的均一なのだという。

母衣の骨格に最も適している「真竹」を毎年コンスタントに取れるように、10月頃間伐作業をしているとのことだ。

中野代表は学生の頃、自身の家の前を和歌祭の渡御行列が練り歩く姿を二階から眺めていたという。
「まさか、自分がこんなに1年中母衣についての段取りをスケジューリングするなんて思ってもみなかった」といいながらも母衣へのこだわりを伝えてくれた。
「和歌祭が開催される5月には立派な母衣を披露出来るように、こうやって一年中竹と向き合って準備をすすめています」。そう話す彼の姿は明らかに母衣の職人だ。




母衣は元和8年(1622)の「次第書」には「ねり 三拾端(さんじったん)の大幌(おおほろ)と記され、長刀振りなどとともに徳川家康の御用を勤めた京都の政商、茶屋四郎次郎清延の四男で文禄2年(1593)生まれの茶屋小四郎が出していた。当時は30着分の重量のある母衣が渡御行列に加わっており、壮観なものであったことが考えられる。この他、御坊町によって赤母衣が3人出されていた。母衣は江戸時代初期の祇園祭(ぎおんまつり)にも登場しており、長刀振や鎧武者とともに武者風流のひとつとして考えられる。
現在、和歌祭には紅白の母衣が登場している。江戸時代中期から法被に化粧回しの出で立ちの奴姿の人物が背負う白母衣が登場する。白母衣は「孔雀舞(くじゃくまい)の所作(しょさ)」を舞っていたことが文化9年(1812)の『紀伊国名所図会(きいのくにめいしょずえ)』に記されており、所作の芸能化が進んだことが考えられる。現在では、大きな白母衣とすこし小ぶりな赤母衣、そして子供による小さな母衣が行列に参加し、「ショモ、ショモ(所望、所望)」という掛け声とともに母衣を左右に3回ずつ舞わしている。和歌祭の午前中には和歌浦の各家を廻り門付けも行っている。
http://wakamatsuri.com/about/event/38-%E6%AF%8D%E8%A1%A3%EF%BC%88%E3%81%BB%E3%82%8D%EF%BC%89.html
和歌祭公式サイトより
武具として強さをみせしめるものであったり、華美な見せ物であったり、時代の背景やそれにまつわる人々とともに変化してきた母衣。
和歌祭で披露される母衣は写真の通り、見た目がとても可愛い物から大型のものまで色々。演舞も勇壮というよりはコミカルな印象だ。日本古来の神々や自然や戦いの世界を描いたジブリの世界観の中に垣間見れる「可愛さ」や「コミカルさ」と母衣は共通するものがあるのかと、筆者は改めて感じた。
歴史ある母衣を大切に守り、竹を育てることから取り組んでいる中野代表をはじめ、たくさんの人々の思いが、この先もずっと続いていくことを期待している。