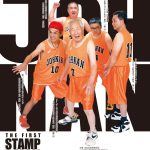「人手が欲しい。でも、ずっとは必要ない」そんな農家の切実な声に、どんな方法で応えていけるだろう。
日本各地の農業現場では、慢性的な人手不足が叫ばれている。特に深刻なのは、繁忙期に一時的に人手が集中して必要になるという「季節性のギャップ」だ。
かつては、近所や知り合いに声をかけ、その都度集まって農作業を手伝ってもらうことが日常だった。
しかし時代は変わった。
小さな農家が減り、代わりに大規模な経営体が地域を支えるようになった今、一時的な人手を確保する仕組みは失われつつある。
この課題に対して、「農家のための人材紹介業」を目指して立ち上がったのが、山下丈太さんが運営する農業特化型の職業紹介「アグリナジカン」。
そして、そこに滞在の場を軸に人と人を結びつけるもう一つの輪を広げようとしているのが、杉浦恵一さんが運営するゲストハウス「スローハウス」だ。
目次
農業の「季節性の人手不足」とどう向き合うか

京都府和束町(わづかちょう)はお茶の産地として知られる場所。大阪生まれの山下丈太(やました・じょうた)さんは、7歳のころに家族で和束町に移住、以来和束町で育った。
大学卒業後、会社員を経て、実家を拠点に農家と農作業をつなぐプロジェクトを立ち上げた。
「地方は疲弊しているなんてよく言われますが、実際には各農家さんが本当に努力してがんばっています。だから私は、そう悲観的には見ていないんです。ただ、規模を拡大している農家さんほど、繁忙期に一時的な人手が必要になる。そのとき、誰か来てくれないかというリアルなニーズが、確実にあるんです」
2019年、農業に特化した人材紹介業を展開するため、株式会社アグリナジカンを設立する。現在、梅の産地として知られる和歌山県みなべ町に移住し事業所を構え、地元の梅農家をはじめ、全国の農家の支援を広げている。
「信頼」をつなぐコーディネーター

「この人なら大丈夫」。そう思ってもらうために、アグリナジカンでは、農家と援農希望者の双方に対して1時間ほどかけてじっくりとヒアリングを行っている。
担当するコーディネーターは、CA(キャリアアドバイザー)とRA(リクルーティングアドバイザー)の両方の立場を担い、信頼関係の橋渡し役として現場に寄り添っている。
その丁寧な対話を起点に、仕組みが動き出す。
まずは、サービスの利用を希望する農家から勤務内容や給与、車の貸し出しや宿泊所の有無といった待遇などを丁寧に聞き取る。それらの情報をアグリナジカンのサイトに掲載し、全国から援農希望者を募っていく。
山下さんはこうした援農希望者のことを「アグリワーカー」と呼び、その挑戦を応援している。ただし農業の現場に立つ以上、気軽な気持ちではなく覚悟を持って臨んでほしいので、ヒアリングのなかでアグリワーカーに対してもその意思もきちんと伝えている。
「お互いの温度感をすり合わせるためには、リアルな対話が何より大事なんです」山下さんは言葉を強める。
現在山下さんを含め、個人と団体合わせて5名がコーディネーターとして在籍している。
印象的なのは、このサービスを利用したワーカーと農家が、勤務期間終了後も連絡を取り続けることについて、アグリナジカンは一切制限を設けていないことだ。「人を呼ぶ仕組みを支えるだけでなく、人との関係を農家が自ら育てていくことも応援したいんです」と山下さんは話す。
ワーカーや農家の意識を育てること。それこそが、アグリナジカンの本当の願いなのだろう。自分たちの利益を優先するのではなく、現場が自立して回っていく未来を目指して、あえて“手放す”。そんな潔さがこの仕組みにはある。
人が人にひかれて集まる場所

こうした「人の流れ」に欠かせないのが“滞在拠点”だ。
若いころから日本中を旅し、2011年3月11日に発生した東日本大震災の直後から震災復興に携わり、そのまま気仙沼に住み着き、現在ゲストハウス「スローハウス」を運営し、全国への展開を目指している杉浦恵一(すぎうら・けいいち)さん。
杉浦さんが震災後に始めたのは、ただ人を迎え入れる場ではなく、「お金がないなら、できることで返してくれればいい」というスタンスで、人と人が支え合う関係性をつくる場を作ることだった。
掃除や料理、DIYなど、それぞれができることを持ち寄って、生活を共に作る。その自然なやりとりの中で、肩書や目的を問われることなく、自分のペースで居場所を見つける若者が増えていった。
それが起点となり2022年に立ち上げた「スローハウス」では「余白を大切に、地域と若者をつなぐ」ことを目指し、単なる宿泊施設ではなく、地域課題を面白がりながら人と人が育ちあう、そんな拠点づくりに取り組んでいる。

そんな杉浦さんは、「農業を通して、その先にある人のよりよい生き方を見つめている」山下さんと出会い、その姿勢にほれ込み心を動かされたという。そこで、滞在者が地域に関わる拠点としてのスローハウスを農業の現場にも生かせると考えた。
「住まいと人」があって農業が続く
かつて農業現場で活躍していたのは、「どこでも寝られる」「不便でも平気」な、ある種タフな人たちだった。農家側も、そうした人が来てくれる前提で、住環境にはあまり気を遣ってこなかったという。
しかし今、農業に挑戦してみたいという“普通の人”が全国から集まりつつある。
だからこそ、水回りの利便性や清潔感といった基本的な住環境が整っていなければ、せっかくの関わりも続かない。
「長く関わる人が増えるなら、住まいの環境が大事になる。汚い空き家じゃ続かない。住みやすさやくつろげる空間が必要なんです」
2025年8月、和束町の山下さんの実家でスローハウス和束が誕生した。運営を担うのは、もともと気仙沼のスローハウスでコミュニティマネージャーを務めていた“ぼんちゃん”こと山中雄斗(やまなか・ゆうと)さん。彼が和束町に移住し、「余白たっぷりの暮らし」を楽しみながら、現在は農業コーディネーターを目指して活動している。

掲げているのは、「大余白時代をつくる」という旗印。暮らしも、遊びも、挑戦も、いっしょに築くシェアハウスを目指して、今まさに宿を手づくりしている最中だ。


また、山口県阿武町(あぶちょう)でも、空き家と農地を活用して“半農半X”のような暮らしを志す人々の拠点となる可能性が広がっている。
農業だけじゃない。「人の流れ」をつくる可能性

この連携は、「農業を支える仕組み」であると同時に、「地域に人の流れを生む仕組み」でもある。山下さんは言う。
現在アグリナジカンを利用する農家や農業法人は、関西地方を中心に全国で140件に及ぶ。
「農業は“人”によってつながれている。だからこそ、農家もワーカーも、その土地や人に関わるきっかけが必要。その入り口になれたらと思っています」
杉浦さんもまた、「まだ見ぬ誰かの『やってみたい』を形にできる場所を、全国に増やしたい」と話す。
農業の現場に必要なのは、作業の担い手だけではない。信頼できるコーディネーターと、安心して滞在できる場所。それがそろったとき、ようやく地域と人がつながる仕組みが生まれるのだ。
季節労働と空き家。どちらも地方の課題として語られがちだが、組み合わせることで、地域の可能性はひらかれる。「ここに来れば、なんとかなるかも」 そんな場所が、各地に生まれ始めている。
「関わる人がそれぞれよりよい生き方をみつけていけるようになればいい」

山下さんは、アグリナジカンの仕組みを全国に広げようとしている。
「農業がとりまく課題などを解決する過程で、人がよりよい生き方をみつけていけるようになればいい。またそれによって受け皿になっている農家さんの人手不足も解決できたらいいですね。農家と働き手、どちらか一方のためというものではなく、どちらにとってもいい時間になるために、どう人がつながっていくのがベストかを日々模索しています」
山下さんの思いは、誰かを管理するためでも、成果を急ぐためでもなく、関わる人たちが“いい時間”を共有できること。その仕組みを丁寧に紡ぎ続けている。
各地で「人手が欲しい。でも、ずっとは必要ない」という農家の声に応えられる人が現れ、現場と人をつなぐ地域の橋渡し役が生まれていくこと。それは、ただの労働力のマッチングではない。農業の営みと、地域に関わりたいという人の思いが、対等な関係として交わる場所。
そんなひとつの可能性を、アグリナジカン×スローハウスの連携は実現しようとしている。そんな場所が、ただの点ではなく、線として面として、日本各地に結ばれていくとき。
農業も、地域も、そして私たちの生き方も、少しずつ変わっていくのかもしれない。

情報
アグリナジカン公式サイト:https://agrinajikan.jp/
アグリナジカンInstagram:https://www.instagram.com/agrinajikan/
スローハウス気仙沼Instagram:https://www.instagram.com/slowhouse_kesennuma/
スローハウス和束Instagram:https://www.instagram.com/slowhouse_wazuka/