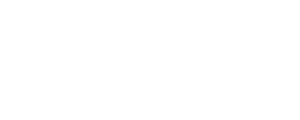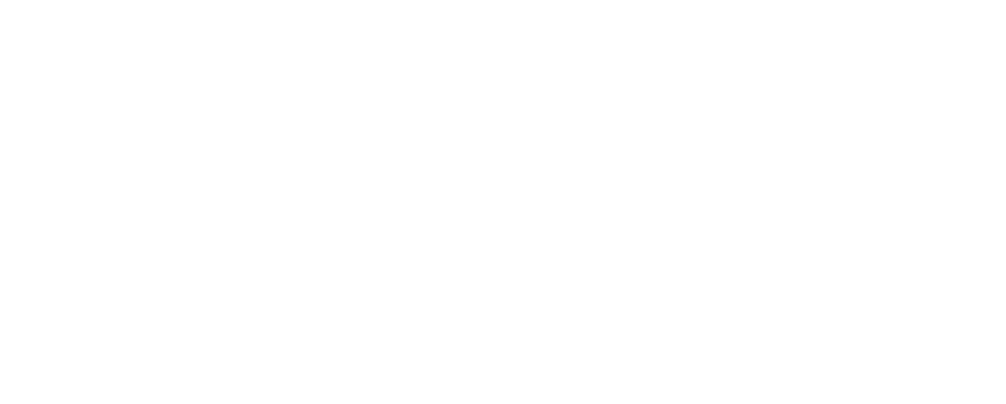先日、広島県熊野町にある熊野筆の老舗「仿古堂(ほうこどう)」を訪れる機会がありました。明治から続く筆の専門店でありながら、どこか家庭的で温かい空気が漂うその空間。展示された棟方志功の作品とともに、日本文化の芯に触れるような感動の時間でした。
そんな中、店内の一角に、鳥居のような朱塗りの枠に吊るされた巨大な筆を発見。まるで「筆の神様」を祭っているようなたたずまいに思わず足が止まりました。


筆を手にとって見比べていると、「こんにちは、筆を探されてるんですか?」と声をかけてくれたのが、店員の古屋敷千代江さん。この方との出会いが、この訪問を忘れられないものにしてくれました。
千代江さんは、筆の毛の種類、太さ、用途について丁寧に教えてくれたうえで、私の使い方や好みをじっくり聞いてくれました。そして、「これ、ピンときたんです」と手渡してくれたのが、程よいコシと繊細な描き心地を兼ね備えた一本の筆。「これは書くだけじゃない、心を映す筆ですね」とつい口にしてしまうほど、手に取った瞬間に何かが通じ合う感覚がありました。
会話が進むうちに、千代江さんとは話がとても盛り上がり、「あら、初めて会った気がしないですね!」と笑い合うほど意気投合。お互いの“ものづくり”に対する情熱や、時代とともに変わる文化への思いを語り合い、すっかり心が温かくなりました。

仿古堂さんの理念「古(いにしえ)を訪ね、古に仿(なら)う」は、まさにこの筆と、この出会いに込められていたと感じています。ハリのある筆先に、どこか懐かしくて新しい気づきが宿っている——そんな一本を、私は大切に持ち帰りました。