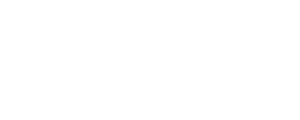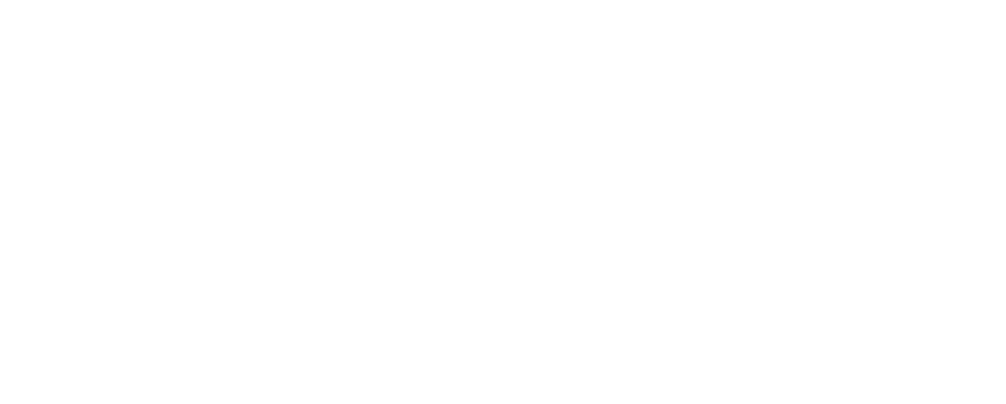秋田市で毎年開催される「秋田竿燈まつり」。新型コロナウイルスの影響で、昨年は戦後初の中止となった。だが、参加者は今年の開催に向けての準備に余念がない。意気込みを伺った。

筆者自身も幼いころからまつりに参加し、「祭りバカ」と言われながら育った。友達が増え、仲間が竿燈をうまく演技できるようになる姿を見て、「自分も負けていられない」と思いながら、現在まで携わっている。
中でも筆者が大人になってから一番大事にしていることは「道具をつくること」で、「継竹(つぎだけ)」は竿燈まつりで最も肝心な道具だ。
竿燈本体は、8メートルの竹に提灯をさげ、重さが最大で50キロにもなるが、持ち手の部分にどんどんと竹を継ぎ、竿燈を高くしていく道具、それが「継竹」である。
継竹を足していけばいくほど、本体の重みにより、竹がしなっていく。そのしなりに耐えられるように、「いかにつくりあげるか」というのがポイントである。
竿燈は夏の行事であるが、実はこの「継竹づくり」は、冬が一番適している。
竹には水分が含まれていて、夏だと、湿気などで多くの水分を含んでしまっている。そんな時期に加工すると、冬場に入って竹が縮んでしまい、削りすぎたり、割れたりする可能性がある。その反面、冬は比較的乾燥した状態となっていて、加工する際削りすぎる心配もなく、割れる心配が少ない。
「継竹」という道具をつくる工程は、
①竹を採取する
②竹をのす(熱を加えて竹を真っすぐにのばすこと)
③乾燥させる(3〜5年)
④加工する
主にこの4つである。
竹は、初冬または初春に採取し、曲がっている竹の節に火を加え、テコの原理でまっすぐに加工していく。それから、3年から5年ほど乾燥させ、乾燥する中で割れなかった丈夫なものが、竿燈の竹として使われることになる。
その後、加工に入る。加工では、それぞれの竹の太さが微妙に違うため、1本1本丁寧にかんなで削り、太さを調整する。また、竹と竹の継ぎ目の部分にはステンレス製の金具を用いるため、接合部分の補強として竹の中に木を入れる。


この一連の作業をできるのは、一握りの職人だけだ。
その職人の中でも筆者の父・重冬(57)は、「継竹づくり」の名人として一目置かれている。
「なまはんかな気持ちで竿燈つくったって、出来の悪いものしかでぎねんだ」と父は言う。
筆者は小さい時から、父の継竹づくりを近くで見てきた。今では自分でも継竹を制作できるようになったが、まだまだ「なまはんか」である。
そんな姿を見ても、父は「出来損ないだな」としか言わず、作り方を教えてくれない。普段、筆者は作業場で、父は自宅で作業する。「自分で覚えたい気持ちがあれば、道具持って俺のところへ見にくりゃあいい」。父はそう言うだけだ。教えてもらったことは、今まで一度もない。竿燈の演技の仕方についても、何にしても、「見て覚えろ」なのである。
今年こそは「良い継竹」で、2年分の思いをのせて竿燈まつりを成功させたい。